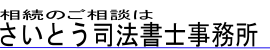任意後見制度とは
saitou
最新記事 by saitou (全て見る)
- 所有権移転などに検索用情報も申し出ることなります。 - 2025年1月25日
- 会社法人等番号も登記事項になりました - 2024年12月26日
- 代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。 - 2024年12月6日

ここでは任意後見制度の概要について解説しています。任意後見契約はどのような内容か、任意後見契約には3つ類型があること、任意後見契約にかかる費用について書いています。
目次
任意後見制度
認知症などで判断能力が衰えてしまうと自分自身で自分の身の回りのことができなくなってしまいます。
税金の支払い、家賃の振り込みといった日常の支払いや希望するデイサービスを利用するにしても、その契約もできなくなっているかもしれません。
身の回りの世話をしてくれる身内が同居していたら別ですが、ちかごろは、いわゆる、おひとりさまのかたも多くなっており、孤独死といった社会問題もあります。
そこで、判断能力が衰えてしまっても自分らしい生き方を実現するために任意後見制度があります。
任意後見人に自分らしい生き方を代わりに実現してもらうのです。
法定後見制度の問題点
よく比較されるのが法定後見制度です。法定後見人には、法律上の強力な力を授けられています。それは取消権というものです。
関連記事【成年後見制度とは? わかりやすく簡単に解説します。】
この取消権により、いったん結んだ契約を取り消してしまうことができます。詐欺や悪徳業者から被後見人を守るためです。
しかし、任意後見人には取消権はありません。
それでは法定後見制度のほうがいいのではないかと思いますが、法定後見にもデメリットがあります。
まず、自分が望んだ人が必ずしも後見人に選ばれるとはかぎらないということです。誰が後見人になるかは、最終的には家庭裁判所の判断です。
また、これは法定後見制度の実情になるのですが、自分の意思とは関係ないところで利用されているパターンが多いのです。
下の表をご覧ください。平成29年1月から12月までの法定後見制度への申立人と本人との関係をグラフにしたものです。
 被後見人になる本人からの申立てよりも、その子供や親族からの申立のほうが格段に多いことがわかります。
被後見人になる本人からの申立てよりも、その子供や親族からの申立のほうが格段に多いことがわかります。
また、次の表もご覧ください。
 こちらの表は、なぜ法定成年後見制度の申立てをしたのかの動機になります。
こちらの表は、なぜ法定成年後見制度の申立てをしたのかの動機になります。
圧倒的におおいのは預貯金を管理したり、解約するためです。
このふたつのグラフから読み取れることは、本人の意向というよりも、その子や親族の意向が優先して法定成年後見制度が使われているという実態です。
本人名義の不動産を売りたいんだけど、あるいは遺産分割協議をしたいんだけど相続人である本人の判断能力が衰えてしまっているから、
関連記事【相続人に認知症の方がいるときの遺産分割協議は?】
といった理由で成年後見制度が使われている面も否定できません。
つまり、法定後見制度では自分の意向が十分に反映されない可能性があるのです。
任意後見契約の内容
その点、任意後見制度は、自分と後見人になる人との契約です。まだ判断能力があるうちにこの契約を結ぶので、自分の意向をことこまかく伝えることができます。
任意後見契約を結ぶ前にまず、今後のライフプランを考えてみましょう。紙に書きだしてみるといいかもしれません。
できるかぎり在宅で介護を受けたいとか、将来、不動産を処分して生活費に充ててほしいといった具合です。
出来上がったライフプランを契約内容に落としこみます。
たとえば、以下のように決めていきます。
1.代理権目録
まず、後見人にどのようなことを代わりにしてもらうかを決めます。いわゆる代理権です。
- 預貯金の振り込み、払い戻し
- 居住用不動産の購入、処分
- 遺産分割の承認、放棄
- 税金の申告、納付
- 医療契約の締結、病院への入院に関する契約
などです。実際はもっと細かいのですが、別紙で代理権目録というものを作成します。
2.報酬の決定
次に後見人の報酬を決めます。法定後見人の場合は自分では決められず、家庭裁判所で決められるので大きなちがいになります。
3.後見開始時期
また、後見がいつから始まるのかも決めます。というのも、任意後見契約を作成した段階では、まだ判断力が十分あるかもしれないからです。
もちろん、作成時から開始させることも可能です。
任意後見契約の内容が決まったら、これを公正証書にします。
必ず公正証書にしないといけません。任意後見契約に関する法律第3条に定めがあるからです。
第3条
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
任意後見契約を結ぶと公証人から法務局に連絡(嘱託)があり、任意後見契約の内容の一部が法務局で登記されます。
任意後見人には任意後見監督人がつく

任意後見を実際にスタートさせるためには任意後見監督人をつけないといけません。
任意後見人が不正をしたり、業務を怠ったりしないように監督する立場になります。
選任をするには家庭裁判所に申立をします。選任には数か月ほどの時間がかかります。
選任されたら、任意後見監督人の氏名などが法務局に登記されます。
任意後見監督人は弁護士や司法書士といった専門後見人が選ばれることがおおいので、報酬も支払わないといけません。
つまり、任意後見だと、任意後見人と任意後見監督人の両方に報酬を支払うことになります。
ただし、任意後見監督人の報酬額は家庭裁判所が決めます。
報酬額の算定には明確な基準はありませんが、資産額が5000万円以下であれば月額1万円から2万円、5000万円を超えたら、2万5000円から3万円といったところです。
任意後見人にできないことを補うには
任意後見人はなんでも代理できるということではありません。任意後見人の仕事は、財産管理と身上監護になります。
財産管理は、自分に代わって公共料金の支払いをしたり、家賃を払ったり、預金をおろしたり、などです。
身上監護は、介護サービスの契約をしたり、入院するための手続きをしたり、などです。
おもに法律行為を代理します。
事実行為はできない
ですから、後見人が介護をしたり、代わりに買い物をしたりというようなことはできません。
これらは、事実行為といいます。
身元保証人にはなれないので
介護施設などに入所する際に身元保証人を要求されることがありますが、後見人は身元保証人にはなれません。
というのも、万が一、介護施設に損害を与えて、身元保証人が請求された損害賠償を支払ったら、身元保証人は任意後見人に払った分を返してくださいと請求できますが、
身元保証人と任意後見人が同一人物だと利益相反になるからです。
関連記事【親子間で利益相反行為になる例は?】
もし、身元保証人を要求されてだれも立てることができないときは、民間の身元保証サービスを考えるといいでしょう。
死後事務はできないので
一般的に人が死んだら、様々な事務処理をしないといけません。死亡届、火葬許可証の交付を受ける、国民健康保険被保険者証の返還、お葬式の手配など、まだまだあります。
これらの事務処理を死後事務といいますが、後見人は死後事務処理はできません。
なぜなら、任意後見契約は被後見人の死亡によって終了してしまうからです。
後見人は代理する権限がなくなるので、できなくなるのです。
後見人以外に身内の人が死後事務をやってくれるのなら、問題ありませんが、そうでない場合は別に死後事務委任契約を結んでおけばいいでしょう。
死後事務委任契約とは、その名のとおり、死後事務を代わりに処理してもらう契約です。
医療行為の同意はできないので
手術をしないといけなくなり本人の同意が必要になっても、その時点で自分はもう意思表示ができなくなっているかもしれません。
しかし、代わりに後見人が同意をすることは現在の法律ではできません。
なぜなら、手術は自分の身体を傷つける行為であり、たとえ親族でもこれに同意するのは憲法違反だと考えられているからです。
それでは、本人の同意が取れないときはどうするのかという問題がありますが、現状は法整備がされておりません。
対策として考えられるのは、、自分の判断能力があるうちに尊厳死宣言書を作成しておくことです。
尊厳死宣言書には、過剰な延命治療を望まない、苦痛を取り除くために緩和治療をしてほしいといったことを記載します。
この尊厳死宣言書をあらかじめ医者に渡しておくのです。
任意後見契約は、将来型、移行型、即効型の3つのタイプがある
任意後見契約には3つのタイプがあります。現在の自分自身の置かれている環境を考えて、適切なタイプを選びましょう。
将来型任意後見契約
今現在は自分の身の回りのことは全部自分でできます、というかたは将来型委任契約がいいと思います。
まず任意後見受任者と任意後見契約を結びます。これでひとまずおわりです。まだ任意後見契約の効果は生じていません。
将来、自分の判断能力が衰えてきたら、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、監督人が選任されたら、任意後見がスタートします。
移行型任意後見契約

今現在、判断力に多少の不安があるという場合は移行型任意後見契約を選びましょう。
こちらも判断力はまだ問題ないので、任意後見契約がいきなりスタートすることはありません。
ただ少しの不安はあるので、始まるまでの間、後見人受任者と見守り契約や財産管理契約を結んでおきます。
財産管理契約は、監督人のつかない普通の委任契約です。
見守り契約は、後見人受任者が月に1度の訪問や電話連絡で自分の状態を図ってくれる契約です。
これにより、適切なタイミングで任意後見をスタートさせることができますし、また、定期的に連絡をとることでコミュニケーションを深めることができるメリットもあります。
また、死後事務委任契約も別に契約しておくことも、もちろんできます。
このように移行型任意後見契約では、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約もあわせるのが特徴になります。
即効型任意後見契約
現在、判断力に不安があるときは、いきなり任意後見契約をスタートさせることもできます。
公正証書で任意後見契約を作成したら、すぐに任意後見監督人の選任申立をするのです。
これを即効型任意後見契約といいます。
任意後見人になれる人
任意後見人には、民法第847条に掲げてある人以外なら、だれでもできます。未成年者、破産者などはできません。
成年後見制度全体に言えることですが、実際は、配偶者、子、親族といった身内のひとか、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職が後見人になるケースがおおいです。
近年は、専門職の後見人が増えています。
身内がいいのか、専門職がいいのかは一長一短です。
身内のメリットデメリット
なんといってもある程度、気心がしれているのが大きいでしょう。コミュニケーションもスムーズに進みます。
また、後見人へは必ず報酬を支払わないといけないというわけではありませんので、任意後見契約の段階で報酬規定を盛り込まないで、無償とすることも可能です。
しかし、任意後見の仕事も責任が重大ですので、まったくの無償にすることも考えものです。
どういうケースであれ、報酬規定はあったほうがいいと思います。
身内を後見人にするときのデメリットですが、財産を横領されるおそれがあるという点です。
厚生労働省の「成年後見制度の現状」によると2017年の全体の被害額は14億4千万円であり、そのうちの9割以上は専門職以外、つまり、親族などになります。
どうしても自分の資産という感じになってしまい、ついつい手を付けてしまったというのが実情ではないでしょうか。
専門職のメリットデメリット
メリットについては、身内の選ぶことの反対になるのですが、横領の被害が少ないという点です。
「少ない」という表現は本来おかしな言い方ではあります。専門職ならば横領はしないのが当然だからです。
現実には残念ながら専門職の横領もあります。しかし、親族などよりも横領のおそれが少ないのは事実です。
また、弁護士や司法書士ならば法律に詳しいという点もあげることができるでしょう。
デメリットとしては、プロに頼むわけですから報酬が必ず発生するという点です。報酬の相場は、管理する財産によりますが、月額3万円からが一般的です。
任意後見人をやめさせるには
さて、なんらかの事情で任意後見人をやめさせたいということもありえます。
任意後見人を辞めさせるには、任意後見が開始(後見監督人が選任された)しているか、いないかで手順がちがいます。
任意後見が開始するよりも前の場合
任意後見が開始する前、つまり、任意後見受任者に辞めてもらうには任意後見契約を解除するというかたちをとります。
解除の理由は問いません。また、一方的に解除を通知してもいいですし、ともに合意して解除でもかまいません。
具体的には、解除するという書面を公証人に認証してもらう必要があります。公証人の認証を受けた書面が要件です。
任意後見開始後
任意後見が開始した後は、家庭裁判所に解任を請求することになります。
どんな理由でも解任できるわけではなく、以下のときにかぎります。
任意後見契約に関する法律 第8条抜粋
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるとき
解任の請求ができるのは、本人だけでなく、任意後見監督人、本人の親族、検察官もできます。
任意後見契約にかかる費用
任意後見契約作成にかかる費用
前述したように任意後見契約は公正証書で作成しないといけません。ですので、公証役場に作成費用を支払います。
また、任意後見契約の作成を司法書士に委任したら、その報酬も支払います。
公証役場でかかる費用は以下の通りです。
- 手数料 1万1000円
- 印紙代 2600円
- 法務局への登記嘱託料 1400円
- 書留郵便料 約540円
- 正本謄本の作成手数料 250円×枚数
司法書士への報酬は地域差がありますが、日本司法書士連合会の平成30年度アンケートによると
東北地区全体の平均値は60615円でした。
任意後見人、任意後見監督人に支払う報酬
任意後見が開始したら、任意後見人と任意後見監督人に報酬を支払います。
司法書士が任意後見人になった場合の報酬は先ほどのアンケートによると、
東北地区全体の平均値は月28464円でした。
また、見守り契約や死後事務委任契約を司法書士と結んだら、別途費用がかかります。
任意後見監督人に支払う報酬は家庭裁判所が決めます。
管理する財産額により変わりますが、月額1万円から5万円ほどです。
まとめ
任意後見契約は、法定成年後見とはちがい、自分自身の要望を取り入れることができる仕組みになっています。
ぜひ、参考にしていただき、自分の老後の安心を設計していただければとおもいます。